9/25~9/27まで岡山大学で行っていたサイエンスキャンプを終え,理数科1年生が学校に帰ってきました!
最終日には2日間の探究活動の成果を他グループの生徒はもちろん,
ティーチングアシスタントの大学院生や大学生,
さらには岡山大学理学部の金田教授,同じく後藤准教授の前で発表しました。
生徒たちにとって初めての発表です。かなり緊張した面持ちでしたが,
立派に成果報告を行うことができました!
それでは,各班の発表の様子と研究成果を簡単に紹介します。
A班「野菜に含まれる塩分量の測定」
モール法と呼ばれる実験法を用いて野菜の塩分量を測定する研究。
トマトやキュウリに比べてダイコンに比較的多くの塩分が含まれていることを突き止めた。
しかしダイコンの塩分量でも1日に必要な塩分量に比べればわずかなため,
野菜の塩分は健康にはまったく害がないという考察を述べた。

B班「室温でできる氷の結晶」
二塩化メチレンという成分を含む接着剤にフェルトをつけてしばらく待つと
室温でもフェルトの周りに氷の結晶が生じる現象を探究し,その反応原理を突き止めた。
様々な条件で比較実験を行い,二塩化メチレン以外に氷の結晶を生じる
物質を探し出した。

C班「様々な水における成分と性質の違い」
硬水と軟水の性質の違いや,水素水や水素を発生させる入浴剤など,
市販されている商品を題材に,身近な水の性質を調査した。
硬水と軟水の違いや,水素に関連する市販の商品には
水素がほとんど含まれていないものがあることを調べ出した。
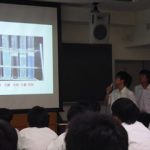
D班「自作電池の作成」
酸化還元反応を利用して電流を発生させるボルタ電池やダニエル電池について
学習し,それらを超える電池を自作することを目標に探究活動を開始した。
机上の計算値を超える電池をつくることはできなかったが,
その原因について考察し,電圧を高める条件を探し出すことができた。

E班「-196℃の世界」
-196℃の液体窒素でいろいろな物質を冷却し,
超低温条件下での物質の様子を研究した。
水分が多い物質ほど固まりやすいことや,
エタノールと水では固まり方が違うことなどを見つけ出した。

写真や動画を使い,相手になんとかして自分たちの成果を伝えようという気持ちのこもった発表をどの班も堂々とすることができました。
発表の最後には質疑応答の時間が設けられており,大学の先生からかなり厳しい質問を突きつけられることもありましたが,”科学的に”成果報告を行う際のポイントを教えていただくことができました。
また,他班の生徒からたくさんの質問が出たことが大変印象的でした。
全ての班の発表終了後,金田教授からご講評をいただきましたが,
短い期間でしっかりと探究活動ができ,
それを堂々と発表できたことを褒めていただきました。
サイエンスキャンプを通して,仮説を立て,実験を通して検証し,
観測できた結果を考察し,それを伝えるという,
「科学的に探究する能力」の基礎を身につけることができました。
これを生かしていくのが今後の活動です。
理数科1年生のこれからの活躍にご期待ください!
